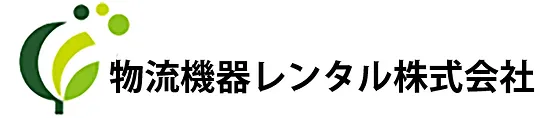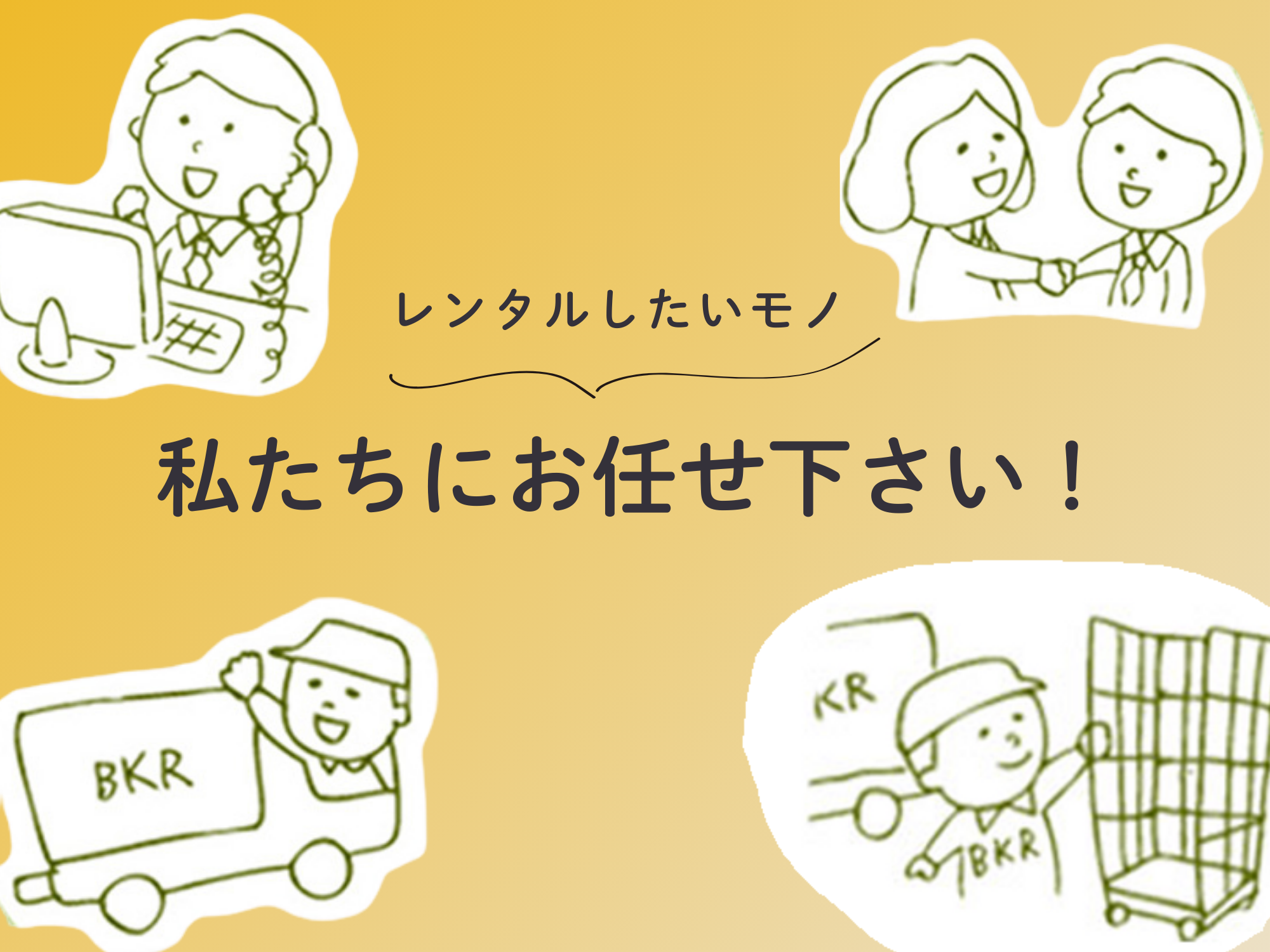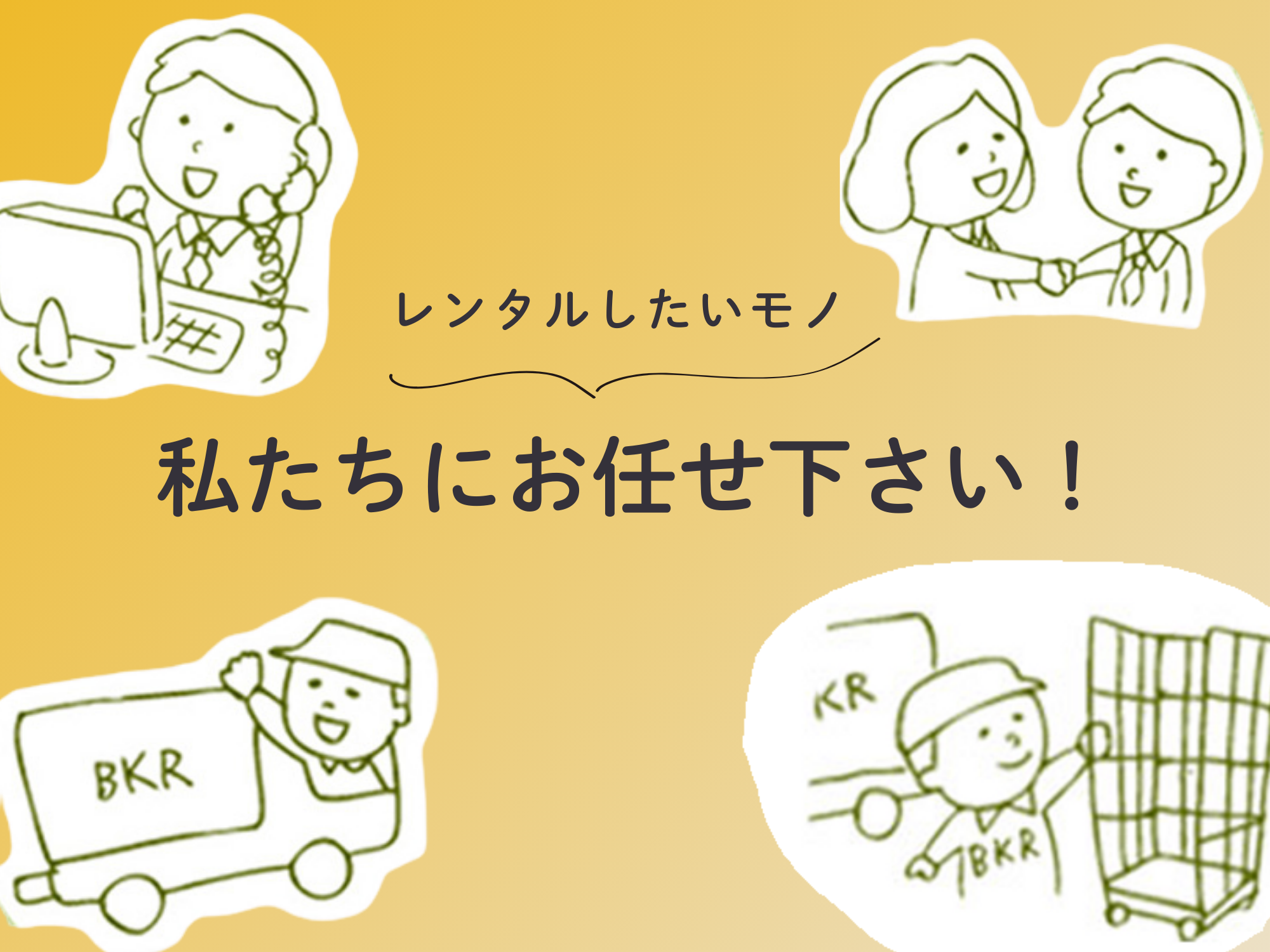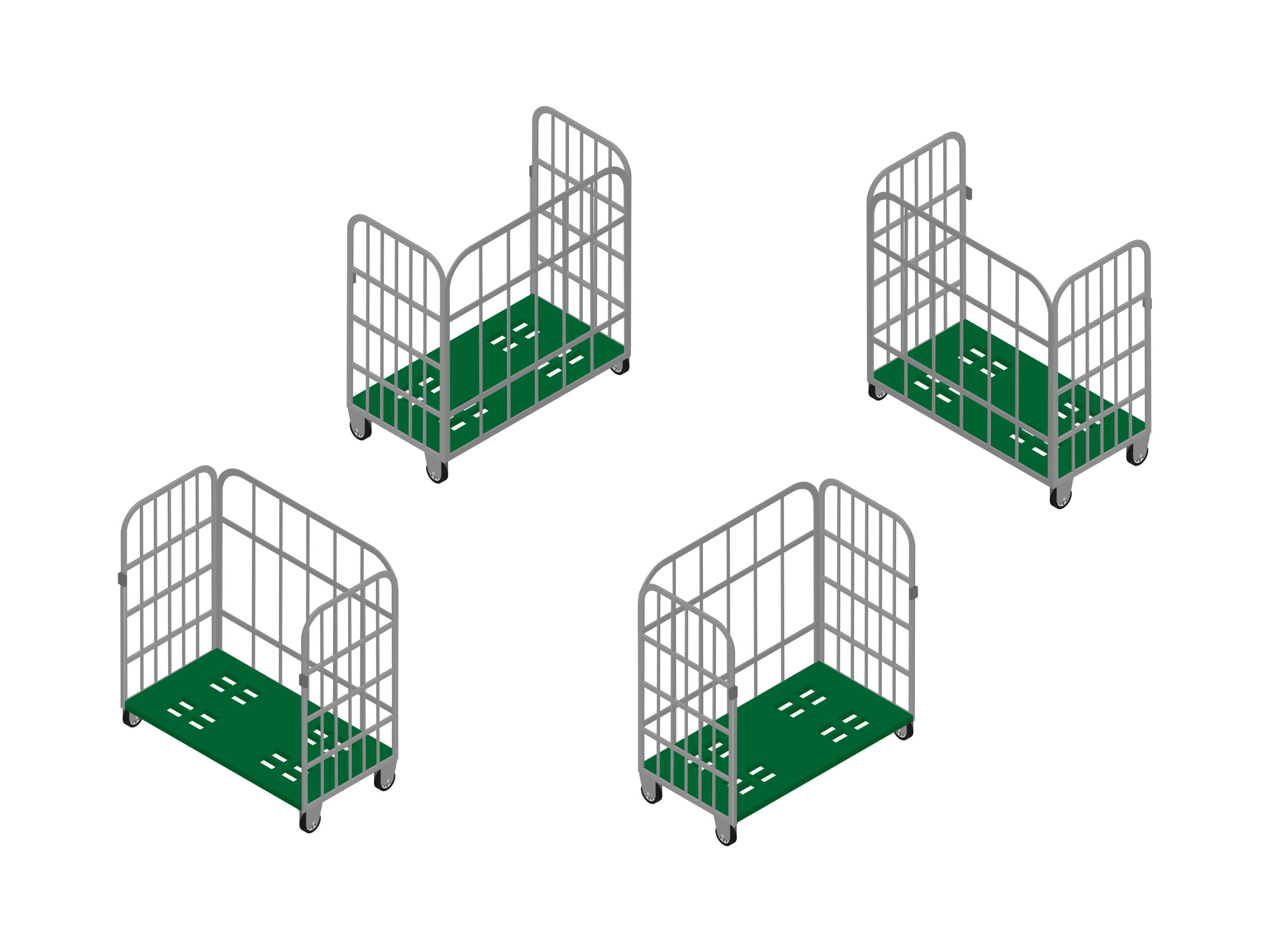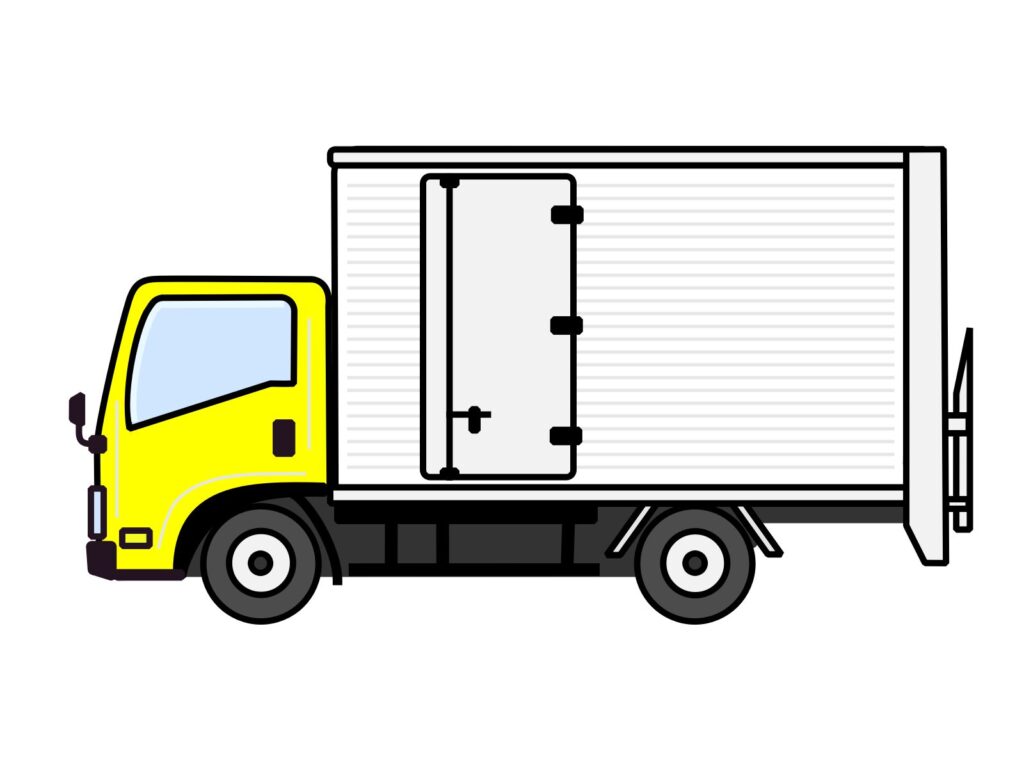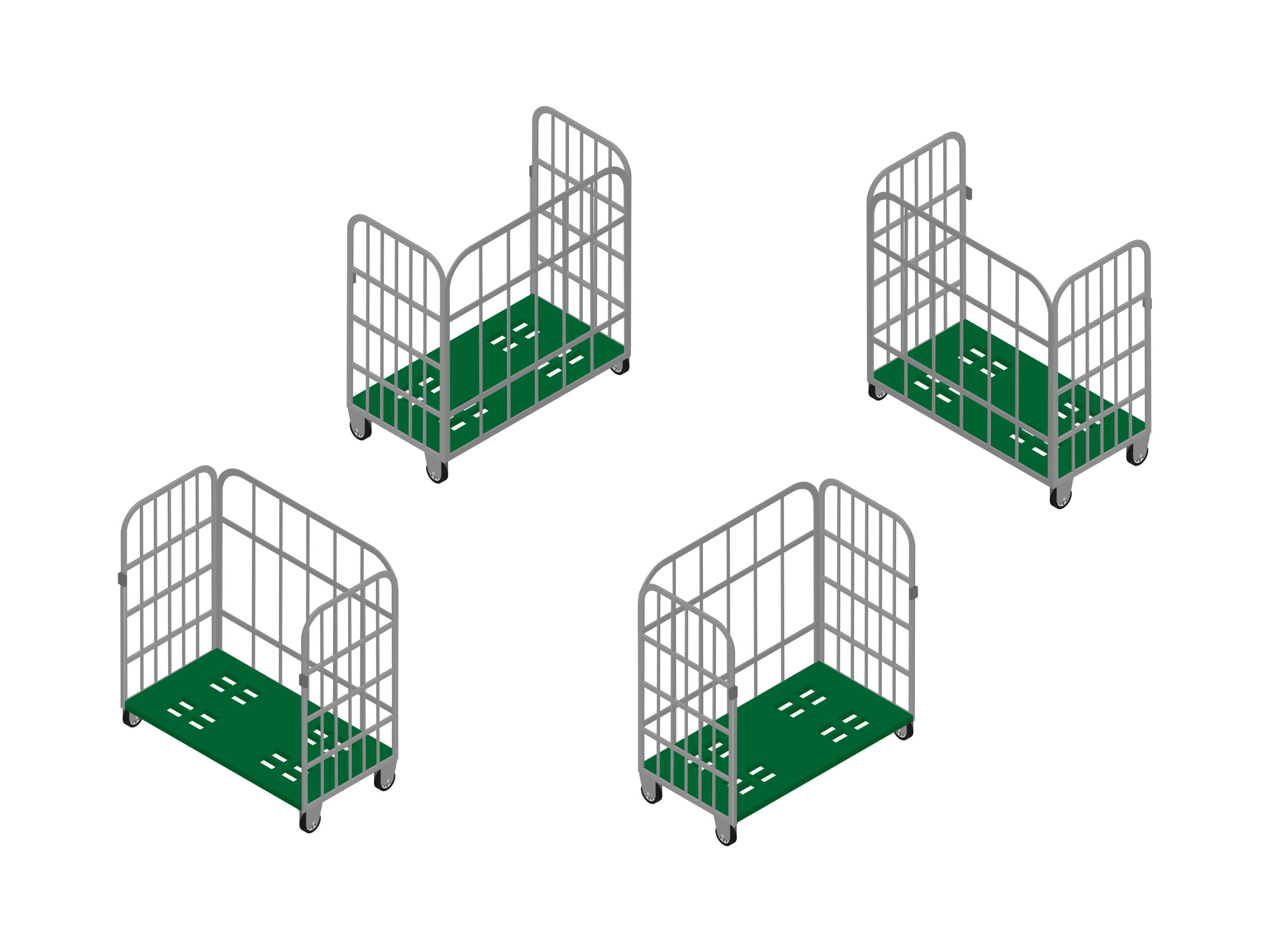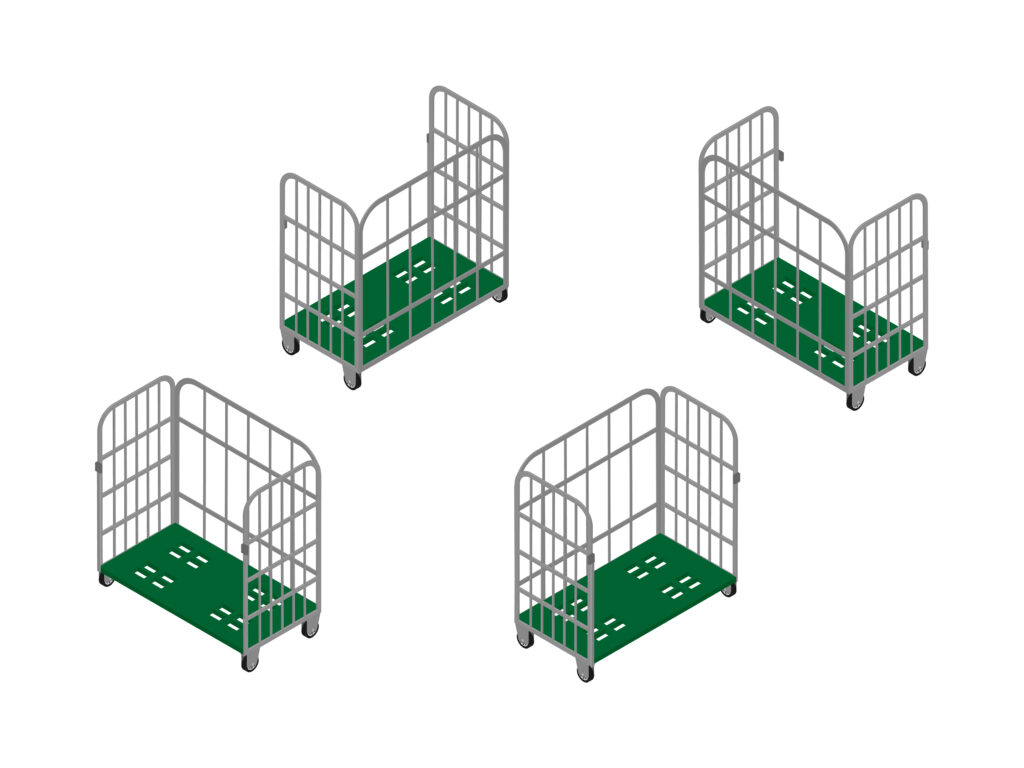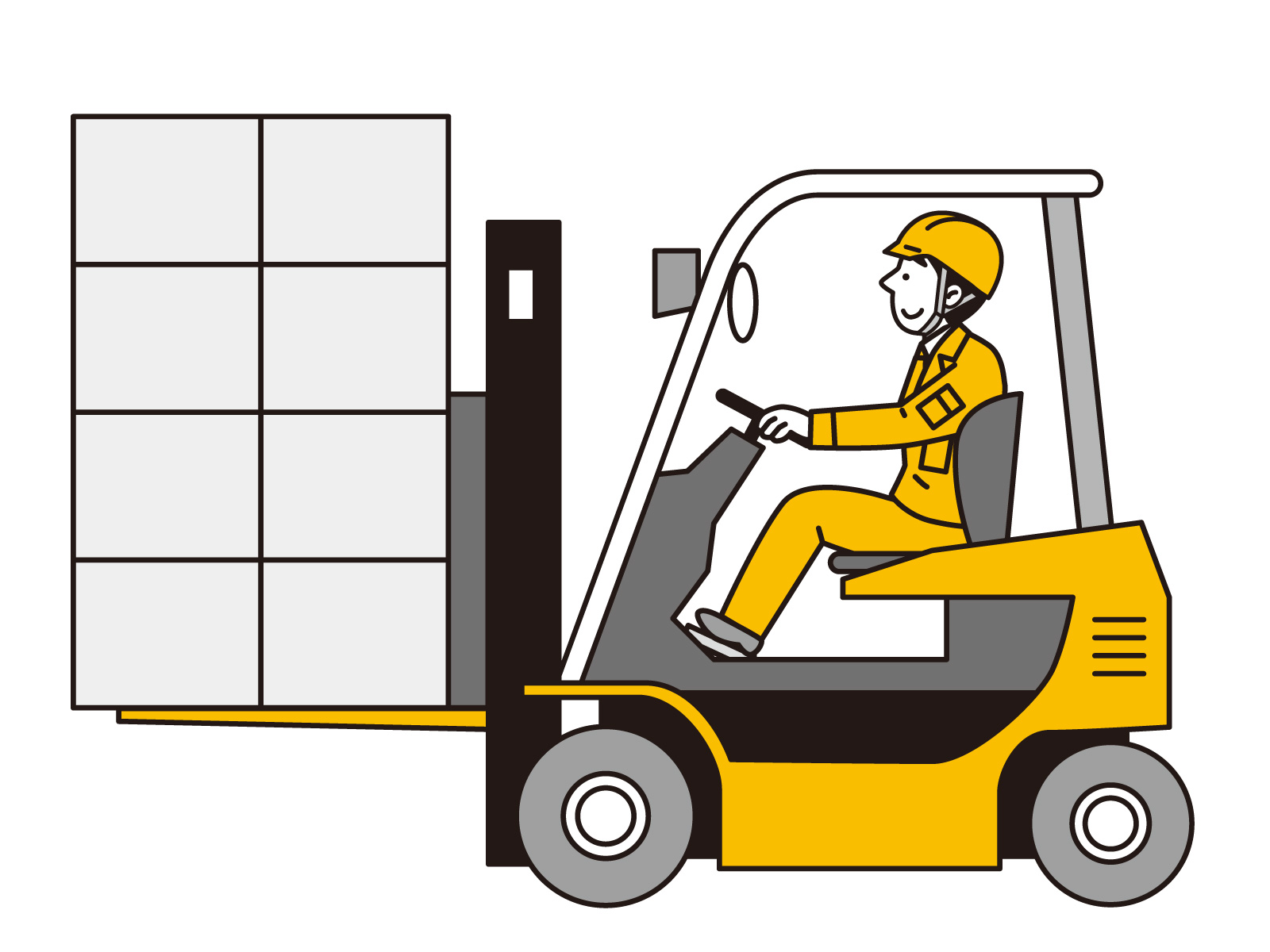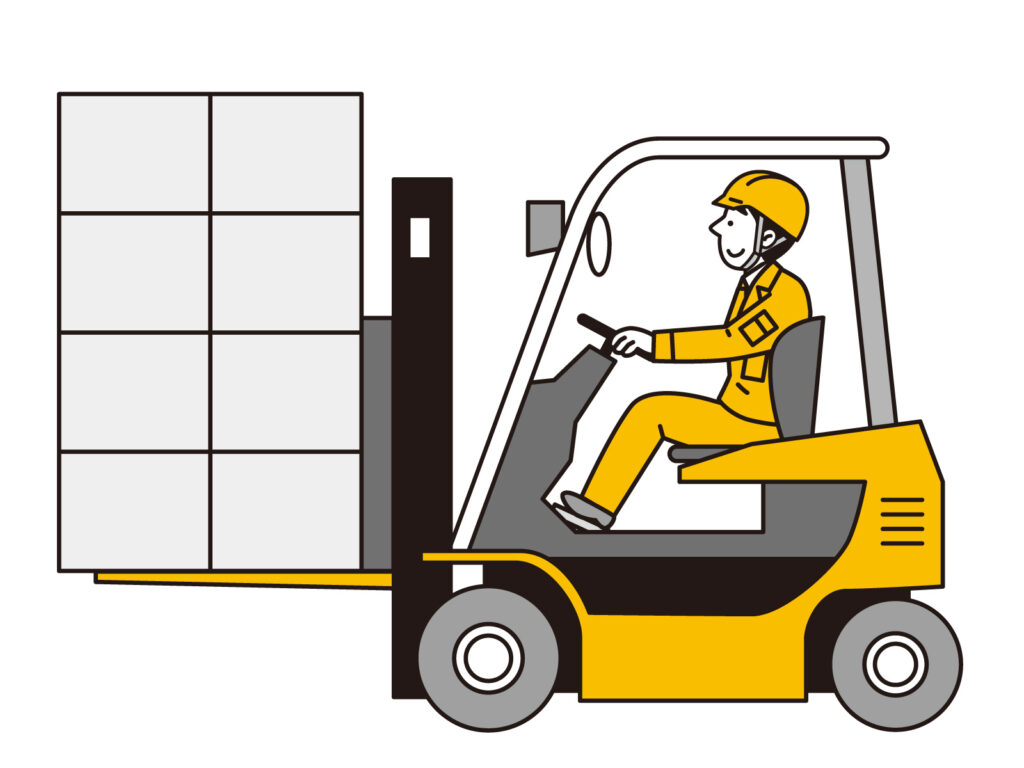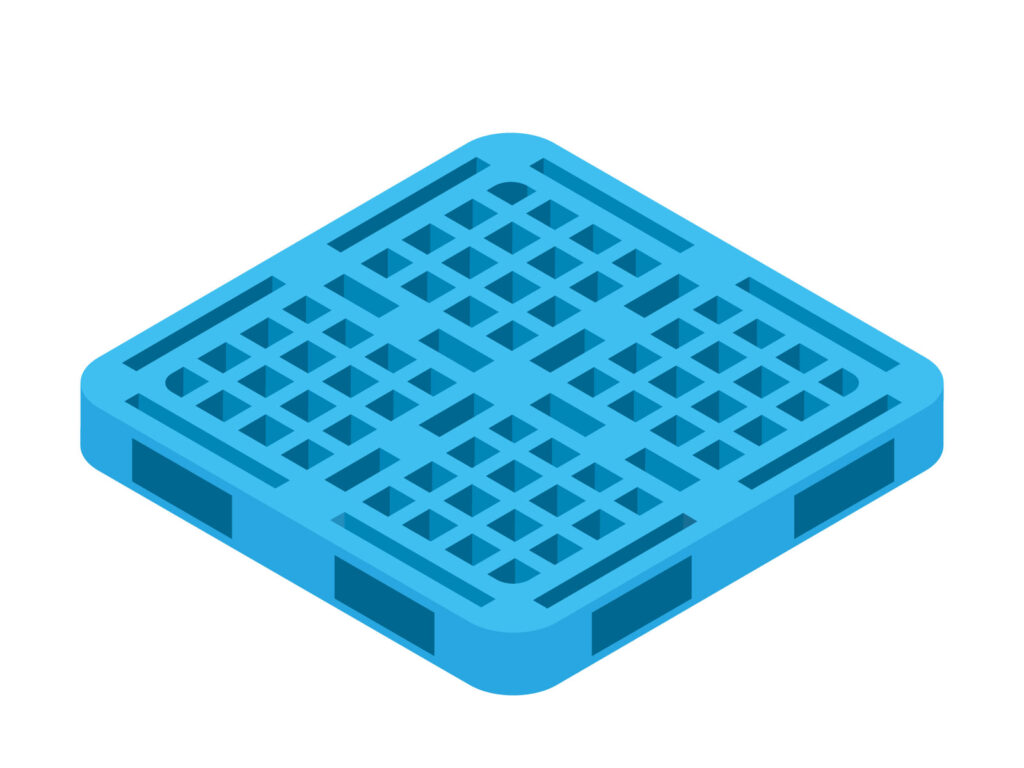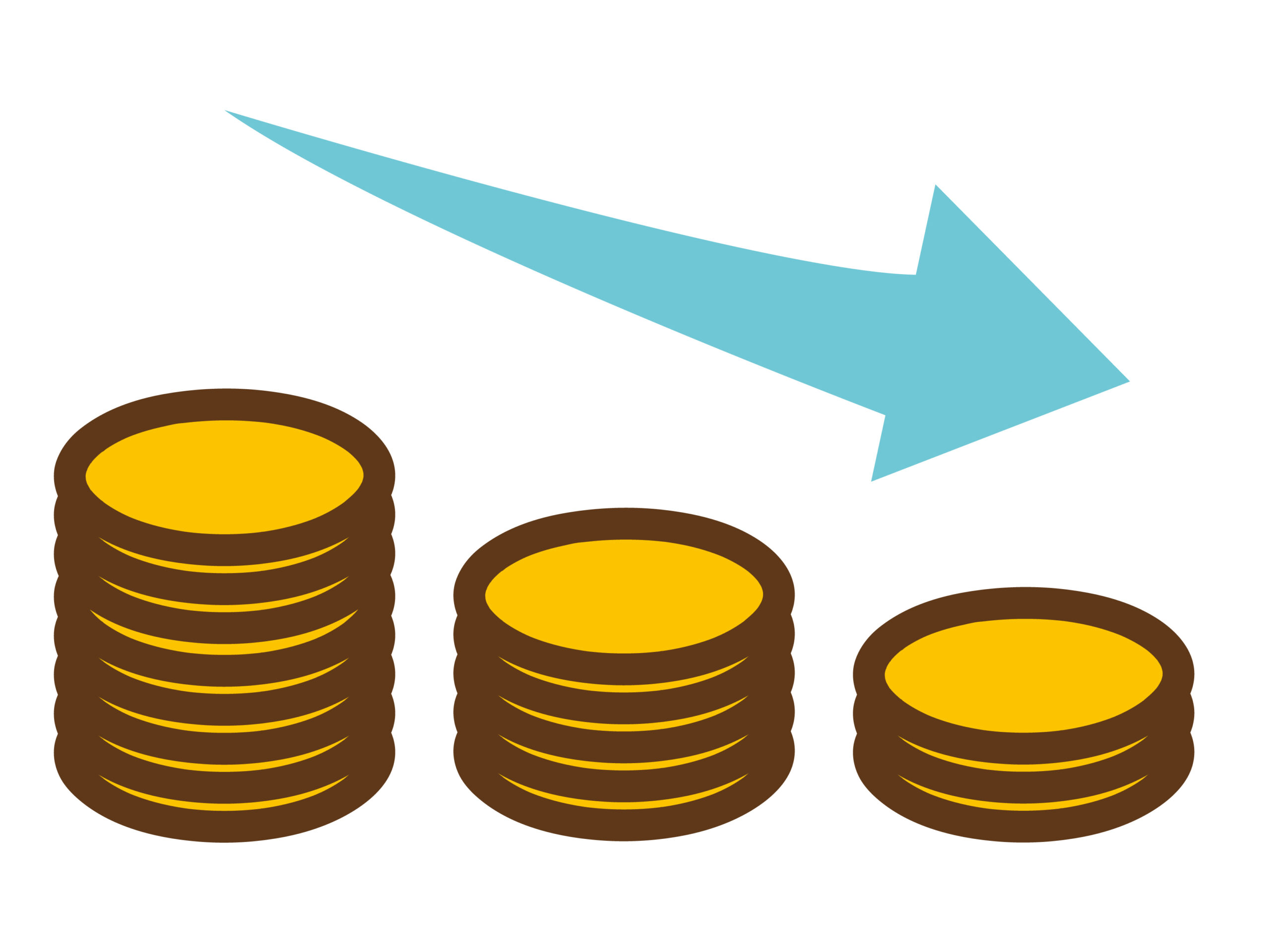共同配送とは、複数の運送業者が提携して同じお届け先へ配送、または距離が近いお届け先の荷物を1つのコンテナやトラックに積んで配送することです。共同配送をすることでコンテナやトラックの積載率が高まり、効率の良い配送が可能となります。
国土交通省による共同配送の提言
国土交通省は、人手不足や生産性向上への取り組み、災害に際しての機能維持、環境問題への対応といった課題に対して企業間で連携するよう提言しています。
複数の荷主や物流企業が輸配送・保管等を共同化する「ヨコの連携」と、発着荷主や物流企業が荷待ち時間の削減に取り組む「タテの連携」を推奨しています。ヨコの連携とタテの連携によって、サプライチェーン全体で物流の効率を向上させるためです。
共同配送のメリット
1、配送を効率化
荷物が少なくても配送しなければならない場合、トラックの空いた部分が無駄になってしまいます。共同配送では1つのトラックにできるかぎり荷物を積載できるため、積載率を高められ、配送効率を向上させることが可能です。
また、荷受人にとっても、複数の運送業者から個別に荷物を受け取るより、一気に受け取る方が作業を軽減できます。
2、ドライバー不足の解消
ドライバー不足は年々拡大しております。
共同配送によって、限られたリソースでも効率よく配送業務を行うことができ、ドライバー不足に対応できます。
3、コスト削減
共同配送によって1台のトラックにまとめて配送できれば、トラックの稼働台数を減らすことができ、ガソリン代や人件費などのコスト削減につながります。
コストを削減できた分、配送料の値下げが可能になる場合もあり、依頼主にとってもメリットです。今後は運送業者、EC通販事業者ともに競争力が求められると考えられるため、配送料の値下げは競争力を高めるためにも重要です。
4、CO2排出量の削減
2023年度における日本の二酸化炭素排出量(9億8,900万トン)のうち、運輸部門からの排出量(1億9,014万トン)は19.2%を占めています(国土交通省HPより)。
SDGsの一環としてCO2削減に取り組むことで、経費が削減できるだけでなく社会的信用の向上にもつながります。
共同配送のデメリット
共同配送のデメリットは以下の3つです。
1、柔軟な対応が難しい
配送を自社のみで行う場合は、急な荷物の増減やルート変更といったイレギュラーにもある程度柔軟な対応が可能です。しかし、共同配送の場合は複数の企業の荷物を積載しており、最適なルートを割り出したうえで配送するため、急な変更に対応するのが難しくなります。
また、1回の配送で複数のお届け先を回るため、細かな時間指定や作業、特定のお届け先への個別対応が難しくなる場合があり、利便性が低下する可能性があるので注意が必要です。
2、配送状況の把握や荷物の追跡が難しい
共同配送は1台のトラックに複数の企業の荷物を積載するため、自社の荷物の場所を追跡して、配送状況を把握するのが難しくなります。
荷物の追跡や配送状況の把握を正確に行うためには、既存システムのリプレースや、他社と共同で使えるシステムを導入する必要があります。
共通システムを使用する場合は顧客情報や社内の情報も共有することになるため、情報の取り扱いや機密保持についての取り決めをすることが重要です。
3、配送料金の設定が難しい
各社独自の配送料金を設定しているため、共同配送を行う際は新たに料金設定を行う必要があります。また、請求方法や支払い方法も各社で異なるため、統一しなければなりません。各社で協議をし、取り決めをすることが重要です。
共同配送に適した荷物
共同配送には、基本的に1つの荷物が少量かつ軽量で、配送頻度が高いものが適しています。荷受人としても、複数のトラックでの配達を個別に受け取るよりも、一気に受け取る方が作業の手間を軽減できる点がメリットです。
共同配送には、以下のような商材の荷物が適しています。
・日用品
・医療品
・食料品
スーパーやコンビニ、ホームセンターなどに配送される日用品は軽量かつ少量のものが多く、毎日配送されるものなので共同配送に向いています。医療品も少量かつ軽量で、箱の形も統一されているため、共同配送に適しています。食料品は、冷蔵・冷凍トラックも効率よく稼働させられるため、燃料費を削減し、空いたトラックを別の配送に回すことも可能になるでしょう。
共同配送に適さない荷物
共同配送には、大きすぎる荷物やいびつな形の荷物、形が一定でない荷物は適していません。
サイズが大きすぎると、他の運送業者の荷物が入らなくなってしまいます。また、形がいびつで一定でないと、配送のたびに積み込み方法を考案しなければならず、かえって非効率となってしまいます。
このような荷物の取り扱いが多い場合は、共同配送に適していないと言えるでしょう。
共同配送に取り組む際の注意点
共同配送は、配送料金や配送ルート、サイズの規格などを複数の企業で協議し、設定する必要があります。しかし、調整や協議が難航する可能性もある点に注意が必要です。
また、荷物の汚破損や紛失といったトラブル時の対処法や責任の所在などについても、事前に決定しておく必要があります。
配送条件を柔軟に変更することが難しく、変更のたびにコストがかかるので、1社のみで配送するよりもコストがかかる場合もあることを念頭に置いて、メリットとデメリットを把握してから取り組みましょう。